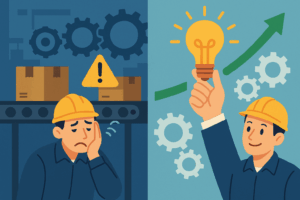製造業にとって生産性の向上は、競争力を高め、収益性を改善するために欠かせません。しかし、生産性向上への道のりは決して簡単ではありませんよね。多くの企業が、どこから手をつけていいのかわからず、迷ってるかと思います。
そこで今回では、製造業が進めるべき生産性向上への3つのステップをお話したいと思います。生産性向上の基本的な考え方から、成功事例に学ぶ具体的な取り組み、そして生産性向上の具体的な手法まで、幅広く触れていきます。さらに、昨今の深刻な人材不足に対応するための方策や、ミスから学んでシステムを改善していくことで品質を担保する方法についても解説。現場のリーダーの方にもわかりやすく、実践的なノウハウをお伝えします。
生産性向上への取り組みは一朝一夕にはいきません。しかし、今回で紹介する3つのステップを着実に進めていくことで、きっと成果を上げることができるはずです。
では今回も読み終えるまでのお時間、しばらくお付き合いいただけますと嬉しいです。
生産性向上の全体像:製造業における3つのステップ、ルール、ツール
生産性向上への取り組みを始める前に、まずはその全体像を押さえておくことが重要です。ここでは、理論とデータに基づいた生産性向上の考え方と、製造業における生産性向上の3つのステップ、そして必要なルールとツールについて解説します。
理論とデータの角度から見た生産性向上とは
生産性とは、投入した資源に対する産出の割合のことを指します。つまり、同じ資源を使ってより多くの製品を生産したり、同じ量の製品をより少ない資源で生産したりすることで、生産性は向上していきます。ようは不良を出ないようにしたり、生産効率を上げれば、結果的に生産性は向上する、というわけです。これが自社にとって、社会にとって良いことであることはわかりますよね。
また、データを活用することで、生産性向上の余地を見つけ出すことができます。例えば、設備稼働率や不良率、リードタイムなどの指標を分析し、工場全体の中のボトルネックを見つけ出すことで、改善すべきポイントを明らかにすることができるのです。
製造業における生産性向上の3つのステップ
製造業での生産性を高めるには、以下の3ステップで進めることがオススメです。ここでは、現場メンバーが理解しやすいように、生産性向上のための基本ステップを簡単に説明しましょう。
生産性向上の第一歩は、現場の作業プロセスをじっくりと観察し、分析することから始めます。この分析を通して、時間の無駄、不要な動き、余計な工程など、生産性を低下させている要因に当りをつけるわけです。例えば、材料の取り出しに時間がかかりすぎる、あるいは特定の工程でボトルネックが発生しているなど、具体的な問題点を見つけ出します。
問題点を特定したら、次にそれらを解決するための改善策を考えて実行します。これは、作業手順をより効率的なものに見直したり、品質を保ちながら時間を短縮できる方法を取り入れることを意味します。また、改善されたプロセスは全員が同じ方法で実行できるように標準化することが重要です。これにより、作業の品質を一定に保ちつつ、生産性を向上させることができます。
生産性の向上を持続させるためには、従業員のスキル向上とモチベーションの維持が欠かせません。このためには、改善されたプロセスに対する適切なトレーニングを提供し、従業員が新しい方法を正確に理解し実践できるようにします。また、目標達成や成功体験を共有することで、チーム全体のモチベーションを高め、継続的な改善活動を促します。
これらのステップを実行することで、製造業の生産性は段階的に向上していきます。重要なのは、現場の状況を正しく理解し、改善のための具体的な行動を取ることです。そして、全従業員が一丸となって取り組むことで、改善努力が持続的な成果を生み出すことができるでしょう。
必要なルールとツール:5S、生産性向上チャレンジ等の紹介・解説
生産性向上への取り組みには、いくつかの重要なルールとツールがあります。
まず、現場の基本的なルールとなるのが5S活動です。整理、整頓、清掃、清潔、習慣(しつけ)を徹底することで、ムダを削減し、効率的な作業環境を整えることができます。
また、全社的な取り組みとして、生産性向上プロジェクトを発足することが生産性向上のツールとしてかなり有効です。期間を区切って、全ての部署が生産性向上に取り組むことで、社内の意識を高め、改善活動を活性化させることができます。ぜひ我が社の重点課題に取り組みましょう。
生産性向上への第一歩は、これらのルールとツールをしっかりと理解し、活用していくことから始めましょう。
成功事例に学ぶ:生産性向上に成功した工場の事例紹介
製造業にとって生産性向上は永遠の課題です。しかし、この課題に対して、効果的な解決策を見つけ、実践に移し、実際に成果を上げている工場も少なくありません。ここでは、生産性向上に成功した具体的な工場の事例を紹介し、その成功要因を解析していくことにしましょう。ぜひこれらの事例から、どのような取り組みが生産性を向上させるのか、そのヒントをつかんでください。
製造業における生産性向上への取り組みの具体的な事例
製造業における生産性向上への取り組みは多岐にわたり、成功している企業では特定のアプローチを通じて顕著な成果を上げています。以下は、実際の企業名を挙げた具体的な事例です。
ダイニチ工業
石油ファンヒーター製造販売を手掛けるダイニチ工業は、複雑化していたアフターサービスの業務を本社のコールセンター部門に機能を集約しました。これにより各営業所の負担軽減と残業時間の削減が実現。顧客サービスの質を保ちながら、効率的な業務運営を実現しています。
大洋工業
電子基板製造の大洋工業では、会議の効率化を図りました。17時以降の会議禁止と会議時間の45分制限、起立会議の実施など新たなルールを設定したことにより、月の平均残業時間を大幅に削減しました。この取り組みは生産性の向上だけでなく、売上・営業利益の増加にも寄与したとのこと。
良品計画(MUJI)
良品計画では、個人に裁量に任されていた業務の標準化を進め、そのマニュアルの整備により、業務効率を大きく改善しました。これらの改善により、無駄な業務が削減され、マニュアルを毎月更新するルールを設定することで継続的な業務改善を実現しました。
トリンプ・インターナショナル・ジャパン
女性下着メーカーのトリンプ・インターナショナル・ジャパンでは、RPAを導入したことにより、受注から出荷までの業務を自動化しました。これにより、作業時間の短縮とミスの削減が実現し、納期管理の徹底が図られたため顧客満足度も向上しました。
陣屋
神奈川県にある老舗旅館の陣屋では、それぞれ個人で持っていた様々な重要情報を業務の一元管理が可能なクラウドシステムを開発し、導入しました。これにより、業務効率化と顧客サービスの向上が実現し、売上の大幅な向上に成功しました。
これらの事例から、生産性向上への取り組みは、業務の集約化、効率化の仕組みづくり、テクノロジーの活用、そして継続的な改善が鍵であることがわかります。成功している企業は、現状に満足せず、常に効率化への挑戦を継続していることが共通しています。
生産性向上の成功要因
これらの事例から明らかな成功要因は、次の3点に集約されます。
重要問題の明確化
ダイニチ工業ではアフターサービス部門の複雑化、大洋工業では会議時間の増大、良品計画では個人に任された業務スタイル、トリンプは受注から出荷までの業務品質と負荷、陣屋は重要情報を個人持ちしていることを自社の大きな問題であることを明らかにしています。つまり生産性を向上させるための自社にとっての重要な問題を明らかにしたうえでの明確な目標設定が、改善活動を具体的な方向へと導きます。
全員参加型の改善活動
それぞれ各社では、それまでの業務を一変させる選択をしたはずです。そうなると必ず起こるのが従業員の反発です。いくら良い改善策だとしても、これまで大切にしてきたことを全否定された理解をすれば、どれだけ裏切られた感が大きくなることか、想像できるでしょうか。そのため、改善への議論は全従業員と重要問題を共有し、その解決のためには従業員そのものが主体となって改善活動に取り組む大切づくりがとても重要です。そのことで、実際の作業に即した効果的な改善案が生まれやすくなります。
技術の積極的な導入
どの改善事例もおそらく、デジタルツールやシステム構築なろ最新技術には積極的だったはずです。トリンプのRPAや陣屋のシステムはわかりやすいですが、ダイニチ工業ではコールセンターシステムの見直し、大洋工業ではリモート会議ツール、良品計画でもマニュアルの整備にツール選択は重要だったはずです。先端技術の存在を知れば、従来の方法では解決が難しかった問題に対しても、効果的な解決策を見出すことができます。
これらの事例を通じて、生産性向上への道のりには、しっかりとした問題定義、具体的な戦略と目標、組織全体の協力と最新技術の適切な活用が不可欠であることがわかります。このような取り組みを自社の生産活動に反映させることで、ぜひ生産性の向上を目指してくださいませ。
生産性向上を目指すための手法:可視化、標準化、最適化
生産性向上を目指す上で、可視化、標準化、最適化は欠かせない手法です。ここでは、生産ラインのボトルネックの発見と解消のための可視化、作業プロセスの標準化によるムダの排除、そして生産ラインの最適化による効率の追求について詳しく解説していきましょう。
ボトルネックの発見と解消:生産ラインの可視化
生産ラインの可視化とは、生産工程ごとの作業時間やサイクルタイム、在庫量などを見える化することです。これにより、生産ラインのボトルネックを特定し、改善のポイントを明確にすることができます。
具体的には、作業者による手動の記録やホワイトボードでの作業状況の可視化、定期的なミーティングでの情報共有などを通じて、データを収集・分析できます。例えば、各工程の作業時間を手動で記録し、そのデータをグラフ化することで、特定の工程での作業時間が長いことが分かれば、その工程がボトルネックであると特定できるのです。
また、違う手法としてはスマートフォンのアプリを活用して、実際の作業時間を計測する方法もあります。スポーツ用の秒数も一緒に録画できるアプリを使って、作業開始から完了までの時間を計測します。これらのデータを集計・分析することで、各工程の作業時間のばらつきや、前後の工程とのバランスを確認できます。こうした現場レベルでの地道なデータ収集と分析が、ボトルネック特定の鍵となるのです。
ボトルネックが特定できたら、その工程の作業手順や設備配置などを見直し、改善策を講じます。例えば、作業の平準化や自動化、並行化などにより、ボトルネックを解消していくのです。
ムダの排除:作業プロセスの標準化
作業プロセスの標準化とは、最も効率的で安全な作業手順を決め、それを徹底することです。これにより、ムダな作業をなくし、品質の安定化と生産性の向上を図ることができます。
標準化の第一歩は、現状の作業プロセスを詳細に分析することです。作業者の動きや、作業時間、使用する工具や材料などを徹底的に洗い出し、ムダがないか検討します。
ムダが見つかったら、その作業を削除したり、より効率的な方法に変更したりします。例えば、必要のない移動や待ち時間をなくしたり、治具を導入して作業を容易にしたりするのです。
こうして改善された作業プロセスを、作業標準書としてまとめ、全ての作業者に徹底します。作業標準書は、図や写真を使ってわかりやすく作成し、定期的に見直すことが重要です。
効率の追求:生産ラインの最適化
生産ラインの最適化とは、生産ラインの設備配置やレイアウト、工程の流れなどを見直し、最も効率的な状態に改善することです。
最適化の第一歩は、生産ラインの現状を可視化することです。工程ごとの作業時間や在庫量、設備稼働率などのデータを集め、分析します。
分析結果を基に、工程間のバランスを取ったり、レイアウトを変更したりして、効率を高めていきます。例えば、工程間の移動距離を短くしたり、中間在庫を減らしたりすることで、リードタイムの短縮につなげるのです。
また、自動化や省人化も効率化の重要な手段です。ロボットの導入や設備の改善により、人手不足の解消と生産性の向上を同時に実現することができます。
生産ラインの最適化は、継続的に進めていくことが重要です。常に現状に満足することなく、さらなる効率化を目指して改善を重ねることが、競争力の源泉となるのです。
人材不足対策と生産性向上:具体的な方法とそのメリット
中小製造業にとって、人手不足は大きな悩みの種です。限られた資金と人材で、いかに生産性を向上させるかが重要な課題となります。ここでは、中小製造業でも取り組める人手不足対策と、生産性向上の具体的な方法について解説していきましょう。
人手不足と生産性問題の背景と現状
中小製造業では、大企業に比べて人材の確保が難しい傾向にあります。特に、若手人材の獲得や熟練工の引退による技能伝承の問題は深刻です。
人手不足は、残業の増加や多能工化の遅れにつながり、生産性の低下を招きます。また、品質トラブルのリスクも高まることが多いため、必ず事前に何らかの対策が必要です。
自動化・ロボット技術とAIを活用した人手不足解消策
大規模な設備投資が難しい中小製造業でも、小型で安価な協働ロボットの導入は比較的容易です。これらのロボットは、人と一緒に作業ができるため、完全な自動化でなくても人手不足の解消に役立ちます。
また、AIを活用した品質検査システムも、手頃な価格帯のものが増えてきました。画像認識技術を使って不良品を自動で検出することで、検査工程の人員を削減できます。
こうした技術の導入は、人手不足解消だけでなく、品質の安定化やコスト削減にもつながります。従業員の負担軽減にもなるため、職場環境の改善にも寄与します。
DX推進と生産性向上のメリットと具体的な取り組み
中小製造業におけるDXの第一歩は、手作業の業務を可能な限りデジタル化することです。例えば、生産実績や在庫量をExcelなどで管理することから始めても大きな第一歩となるでしょう。
また、クラウドサービスを活用するのも有効です。生産管理や在庫管理、勤怠管理などのシステムをクラウドで利用することで、初期投資を抑えつつ、業務の効率化を図ることができます。
さらに、タブレット端末を活用した作業手順書の電子化や、動画を使った作業者教育なども、中小製造業でも比較的取り組みやすいDXの事例です。
DXを推進することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 業務の効率化による生産性の向上
- ペーパーレス化によるコスト削減
- データの見える化による問題点の早期発見
- 作業者教育の効率化と技能伝承の促進
ただし、DXの推進には、従業員の理解と協力が不可欠です。デジタル化のメリットを丁寧に説明し、従業員の意識改革を図ることが重要です。
中小製造業が人手不足と生産性の問題に立ち向かうには、自社の規模や予算に合った方法を見つけることが大切です。協働ロボットやAI、クラウドサービスなど、比較的導入しやすい技術を活用しながら、地道にDXを推進していくことが、これからの中小製造業に求められているのです。
生産性向上への道のり:ミスから学び、システムを改善し、品質を担保
生産性向上は一朝一夕には実現できません。ミスから学び、システムを改善し、品質を担保する地道な努力の積み重ねが必要です。ここでは、中小製造業の生産現場でのミス原因とその解消法、システム・設備の問題点とその改善策、そして品質を担保するための生産・製造管理方法について解説します。
生産現場でのミス原因とその解消法
中小製造業の生産現場では、人的ミスが発生しやすい傾向にあります。その原因としては、以下のようなものが考えられます。
- 作業手順の不明確さ
- 教育・訓練の不足
- 疲労や集中力の低下
- コミュニケーション不足
これらのミスを防ぐには、作業手順の標準化と明文化が重要です。作業手順書を作成し、定期的に見直すことで、曖昧さをなくしていきます。この手順書作成そのものを管理者だけで進めることはオススメできません。管理者は手っ取り早く自分でやることを選択しがちですが、当事者である作業者を巻き込んで手順書をつくることで、周知徹底を同時に進めることができます。
また、OJTを重視し、先輩社員が丁寧に指導することも大切です。新人社員の教育に時間をかけることは、長期的には生産性向上につながります。
さらに、適度な休憩の確保や、コミュニケーションの活性化も、ミス防止に役立ちます。現場の声を吸い上げ、改善に活かす風土を作ることが重要です。
システム・設備の不足・問題点とその改善策
中小製造業では、予算の制約からシステムや設備の更新が遅れがちです。更新が遅れた古い設備はトラブルの原因となり、生産性を下げる要因ともなり得ます。
こうした問題を改善するには、計画的な設備投資が欠かせません。単に新しい設備を導入するだけでなく、メンテナンスの徹底や、予備部品の確保など、トラブル対策も重要です。
また、生産管理システムの導入も検討すべきです。市販のパッケージソフトを利用することで、比較的安価に生産管理の効率化を図ることができます。
設備やシステムの改善は、一時的なコスト増につながります。しかし、長期的に見れば、生産性向上やコスト削減のメリットの方が大きいはずです。
品質を担保するための生産・製造管理方法
品質の確保は、中小製造業にとって重要な課題です。大企業のように高度な管理システムを導入することは難しいかもしれませんが、基本的な管理方法を地道に実践することで、品質の安定化を図ることができます。
不良品の流出を防ぐ仕組みの設置
まずは、日々の品質チェックを欠かさないことが大切です。全数検査が難しい場合は、抜き取り検査を行いましょう。検査基準を明確にし、不良品の流出を防ぐことが重要です。
個人の努力に頼らず、チーム全員で取り組む
また、作業手順の標準化も品質管理の基本です。作業手順書を作成し、全員が同じ手順で作業できるようにします。手順書は写真や図を使ってわかりやすくすることが大切です。
シンプルなQC活動のスタート
さらに、不良品の発生原因を突き止め、再発防止策を講じることも重要です。不良品が発生した際は、原因を特定し、作業手順の見直しや設備の改善など、必要な対策を速やかに実行しましょう。
品質教育に時間とお金をかける
加えて、従業員の品質意識を高めることも欠かせません。品質の重要性を繰り返し伝え、全員が品質向上に取り組む意識を持てるようにします。前述のQC活動の学習などを通じて、品質改善の提案を引き出すことも効果的です。
ISO9001の考え方を参考にする
大企業のようにISO9001などの品質マネジメントシステムの導入は、規模の小さな企業にとってはハードルが高いかもしれませんが、その考え方を参考にして、自社なりの品質管理体制を築くことは可能なはずです。
品質管理はお客さまの立場を想像してみれば、けっして難しい取り組みではありません。基本的なことを地道に実践することが何より大切です。全員が品質向上への意識を持ち、日々の管理を怠らないことが、中小製造業の品質を支える鍵となるでしょう。
まとめ:製造業が進めるべき生産性向上への道
さて、いかがだったでしょうか?生産性向上への道を歩むのはそれなりの覚悟が必要です。たしかにこの道のりは決して平坦ではありませんが、今の時代を生き抜くために避けては通れない課題です。
複雑化する要素で競争が激化する中、生産性を上げることは企業の存続に直結します。だからこそ、現場の一人ひとりが知恵を出し合い、創意工夫を凝らしながら、改善を積み重ねていくことが必要になっているんです。
生産性向上への道は、一朝一夕では完結しません。それは終わりのない旅のようなもの。しかし、その旅を通じて、従業員は単純作業だけではない課題解決を楽しむ選択肢を用意できると同時に、企業は強靭な体質を手に入れることができるのです。
さあ、今すぐ生産性向上への一歩を踏み出しましょう。全社一丸となって、このテーマに立ち向かいましょう。皆さんの汗と努力が、必ずや会社の未来を切り拓くはずです。
もし、確認したいことがあれば以下まで気軽にZOOMでの無料相談をお申込みいただければと思います。
滋賀県よろず支援拠点> https://www.shigaplaza.or.jp/yorozu/contact
※ 西本を指名すれば、全国どこからでも申込み可能です。
それでは今日はここまでです。今後とも宜しくお付き合い下さい☆
長文乱文を最後まで読んでくださりいつもありがとうございます♪
すべては御社の発展のために、すべてはあなたの笑顔のために