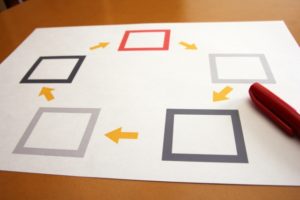QC活動の進め方入門サイトを運営して
QC活動の情報を発信していますと
何人かのヒトから質問が寄せられます
今回はそんな質問に答えた内容を
紹介していくことで
さらなるQC活動の理解に
つなげていただければ幸いです
Q1:データはどこまでとればいいですか?
| 製造業のQC活動を実施していて、部品の強度の実態を詳しく知るためにたくさんデータをとったのですが、結局使わないことがありました。できるだけ詳しく細かく取ったほうがよいのはわかっているのですが、ムダなデータを取ると思うとあまり気が進みません。データとは結局、どこまでとればよいのでしょうか? |
確かに悩ましい質問ですよね
詳細にデータを取得するのには
それなりの労力がかかりますから
最後にムダになることを考えれば
やめたくなる気持ちも理解できます
A1:データをとる目的を明確にしよう
『データでものを言う』という姿勢は
とても大切な考え方です
そんなデータの取る時には
そのデータで何を知りたいか?
その目的に応じたとり方を考えます
データの数が少いと
わかることも限られてしまいます
たとえばデータが1つだけだとすると
ばらつきの情報は得られませんよね
午前中にサンプリングした
数個のデータだけだとするなら
午後も含めた1日の変化を
知ることはできません
たとえば
強度データの時間経過の変化を
知ることを目的と置いたとします
そうすると加工時間の順番に
継続してデータをとることが必要です
また
工程の状態を管理図で解析したいなら
20~30個程度の群の数が必要です
このように目的に合わせてデータの
とり方を考えていくことが大切です
さらにヒストグラムを用いて
強度分布の全体像を把握したいなら
より多くのデータが必要になります
この場合データは100個程度必要で
日々製造した製品の強度データを
たくさん集めていくことになります
そうなると大変ですよね
でもこういった目的がはっきり
しているなら集める甲斐もあります
さらにライン別に違いがあるか
作業者別ではどうかなど
調べたいことのアウトプットを
イメージして全メンバーで共有して
データ集めを進めていってください
QC活動Q&A①まとめ
データの集め方にも
工夫の余地があります
今回の活動で必要なデータだと
認識が強まったなら
自然にあつまる方法も検討すべきです
たとえば製品シートに記入するよう
欄を工夫して増やしてみたり
自動記録ができるよう
設備を改造したりも検討の範疇です
ぜひ考えてみてください
それでは今日はここまでです
今後とも宜しくお付き合いください☆
長文・乱文を最後まで読んでくださり
いつもありがとうございます♪
すべては御社の発展のために
すべてはあなたの笑顔のために