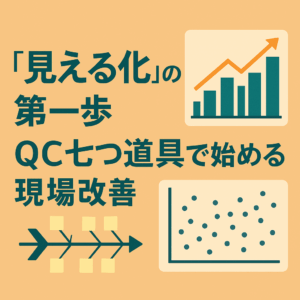これまでの第1回では、製造業を取り巻く環境変化を踏まえ、「なぜいま、生産性向上が不可欠なのか」を整理しました。続く第2回では、その実現のために必要な基本的な視点として、VE(Value Engineering)手法を取り上げ、「改善=コストカット」ではなく「価値最大化」という考え方を提示しました。

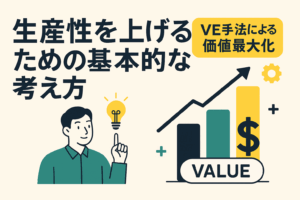
第3回となる今回は、改善活動が上手くいっている職場とそうでない職場について、考えていきたいと思います。
皆様の職場でも、QC活動や改善提案、ヒヤリハットなどの制度によって、従業員の自主的な改善を促す制度が導入されているのではないでしょうか。
ところが、これらの活動が長続きせず、形骸化してしまっている職場も多く見受けられます。
掲げられた目標が曖昧で、やがて「やること自体が目的化」してしまったり、あるいは目標自体は明確だったとしても、特定の担当者だけに依存して属人化したり、成果が見えないまま現場の負担感だけが増していく状況を沢山目の当たりにしてきました。
一方で、制度として定着させ、成果を積み重ね続けている職場も確実に存在します。
本稿では、まず「改善活動がうまくいかない工場に共通する典型パターン」を整理した上で、制度として改善を回している成功事例を紹介します。
そのうえで、成功企業に共通する仕組みの要素を抽出し、最後に読者の皆さまが明日から導入できる小さな実践アイデアを提示します。
改善活動が定着しない工場に共通する“4つの典型パターン”
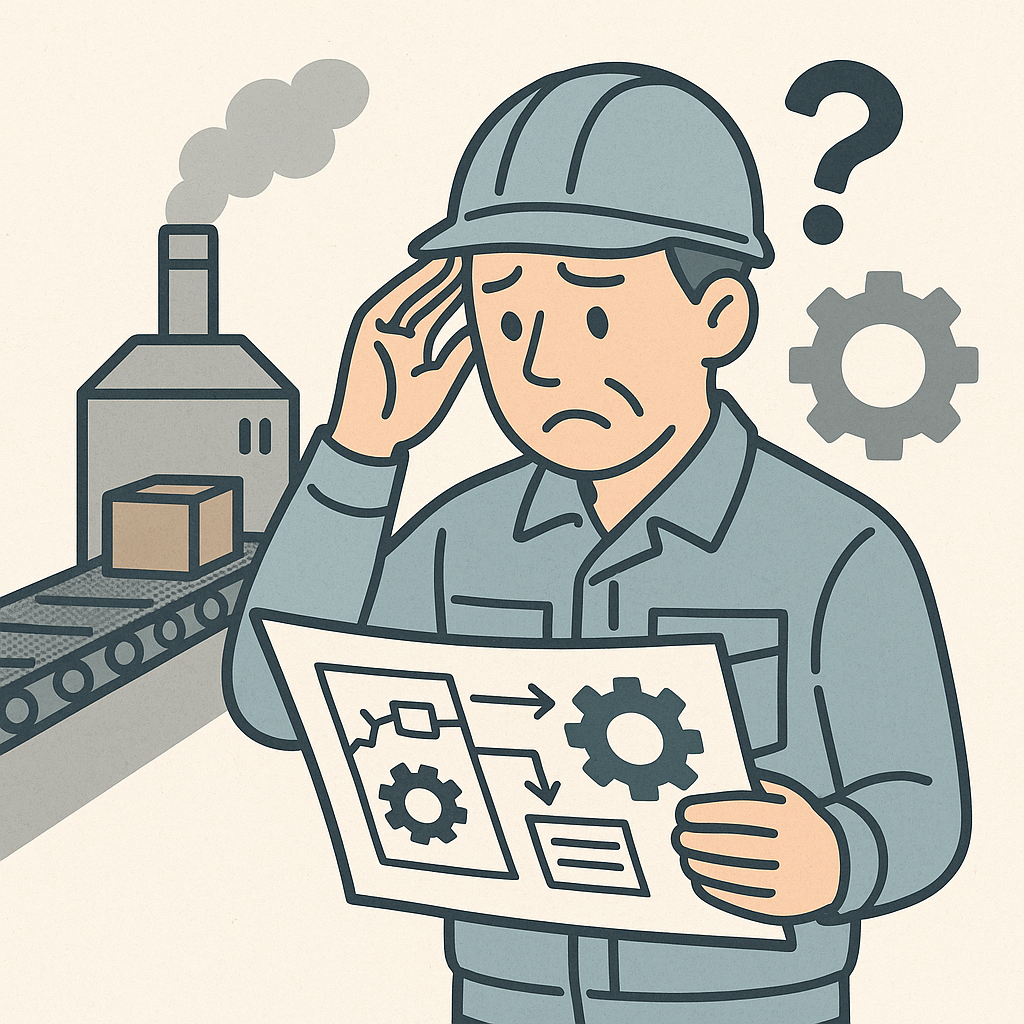
多くの工場で導入されている改善活動ですが、そのすべてが成果を挙げているわけではありません。
むしろ、「やっているつもり」になって実質的な改善につながらないケースもありますし、そもそも理念だけが掲げられ、現場では何も動いていない職場も少なくありません。
ここでは、「なぜ改善活動が定着しないのか」を4つの典型的なパターンに分類して整理します。
目的が曖昧な改善活動の実態
改善活動が空回りする最大の要因は、「何のために行うのか」という目的が共有されていないことです。
例えば、「改善提案を月に10件出そう」といった数値目標だけが先行すると、提案すること自体が目的化し、本来目指すべき生産性の向上や安全性の確保には結びつきません。
また、提案の中身も、「自身に負担なく対応可能なもの」が多くなり、品質の低下が懸念されます。
つまり、見かけ上は改善活動が活発に行われているように見えても、表面上の改善に留まり、本質的な課題は未解決のまま取り残されてしまうのです。
さらに、このような数値目標は得てして現場の従業員には「改善」ではなく「ノルマ」として捉えられてしまい、従業員の負担が増え、疲弊を招きます。
本来は未来を良くするための活動であったものが、真逆の結末を招いてしまうこともあり得るのです。
成果が感じられない活動の問題点
改善活動が続かない2つ目の要因は、現場の従業員が効果を実感できないことです。
たとえば、数値目標を達成するために、必死に改善活動を行ったものの、それで得られた効果が、作業時間がわずかに短縮されただけで日常業務の負担感が変わらなかったとして、従業員は次の改善活動に向けた努力を行うでしょうか。
また、数値上は改善が出ていても現場に還元されなかったりした場合、従業員はどのように思うでしょうか。
多くの場合、従業員は「やっても意味がない」と感じてしまい、改善活動へのモチベーションが低下してしまいます。
また、特定の工程だけに改善が反映される場合も、他の従業員には変化が届かず、活動の広がりを実感できません。
特に中小企業においては、現場主導で行われる改善活動には限界があり、劇的な変化を実感する機会はそう多くはありません。
改善の成果が現場にとって実感を伴わないものであれば、活動は次第に形骸化し、「やれる範囲で負担のないことをやっておこう」という空気を生み出します。こうした状態では、改善活動が本来の力を発揮することはできません。
属人化(特定の人頼り)のリスク
改善活動が長続きしない3つ目の要因が、活動が特定の人に依存してしまう「属人化」です。
属人化の厄介さは、一見すると改善が順調に進んでいるように見える点にあります。
熱心なベテランやリーダーが旗振り役となり、自ら率先して改善を進めていけば、活動そのものは目に見えて回っているように感じられます。
しかし実際には、その人の頑張りでしかなく、組織全体として改善の仕組みが根付いているわけではありません。
そして、その人が異動や退職、あるいは休職などで現場から離れた瞬間に、従来の改善活動が継続困難となり、初めて「誰も引き継げる人がいない」という現実に直面します。
組織としての改善力を高めるどころか、活動の持続性が危うくなってしまうのです。
さらに、同じ人ばかりの意見や提案が採用され続けると、他の従業員は「どうせ◯◯さんの案が優先される」と感じ、受け身の姿勢になってしまいます。
これでは、視野が狭くなってしまい、見落としや優先順位の誤りなどが発生してしまう可能性が高まります。
結果として改善活動は狭い範囲に閉じ、組織全体での成長にはつながりません。
改善活動を持続させるためには、個人の頑張りに依存せず、組織全体で共有できる“仕組み”に落とし込むことが不可欠です。
評価と連動しない改善の限界
改善活動が定着しない4つ目の要因は、活動の成果が人事評価や組織の成果と結びついていないことです。
従業員が数値目標の達成や、自身の職場を良くしたいと一生懸命に提案や取り組みを行っても、それが給与やキャリア形成に反映されなければ、「やっても意味がない」と感じてしまいます。
改善に費やした時間が本来業務の負担増と受け止められれば、なおさらモチベーションは下がってしまうでしょう。
一度、「やらないもの勝ち」という空気が組織に蔓延してしまったら、それを払しょくすることは非常に時間が掛かり困難です。
一方で、逆に「提案件数を評価基準にする」といった単純な制度設計を行うと、今度は質の伴わない提案が乱発されるリスクが生まれます。
その結果、現場は数をこなすことが目的化し、改善の本質から遠ざかってしまいます。
改善活動を持続させるには、活動が正当に評価され、従業員にとっても「やる意味がある」と感じられる仕組みが必要です。
評価と連動していない改善は、結局「誰のための活動なのか」が曖昧なまま終わり、定着にはつながりません。
改善を“仕組み”として定着させている企業の事例

前章では、改善活動が形骸化する典型的なパターンとして「目的の曖昧さ」「成果の実感不足」「属人化」「評価と非連動」を取り上げました。
いずれも共通しているのは、改善が制度や仕組みに落とし込まれていないことです。
改善を個人のやる気や一時的な熱意に依存したままでは、活動はどうしても持続しません。
だからこそ、改善を「仕組み」として組織に根付かせることが不可欠なのです。
この点で注目されるのが、村田製作所と枚岡合金工具の取り組みです。
両社は改善を制度化し、従業員が効果を実感できる環境を整えることで、成果を積み重ね続けています。
以下では、それぞれの具体的な事例を紹介します。
村田製作所:IoT・AIを活用した設備稼働の見える化
村田製作所では、IoTやAIを導入する前から「改善の属人化」という課題を強く認識していました。
ベテラン技術者の勘や経験に依存した改善は、その人材が抜けるとノウハウごと消失してしまうリスクがあったのです。
そこで同社は、設備稼働データをIoTで収集し、AIで分析することで「誰でも同じ情報に基づき改善できる仕組み」を構築しました。
従業員はデータを見ながら議論できるため、改善の方向性が属人化せず、組織全体で共有できる“共通言語”として機能しています。
さらに、数値はリアルタイムで公開され、改善前後の効果がすぐに分かる仕組みになっています。
従業員にとっては「やって終わり」ではなく、「成果が返ってくる」活動として認識されるため、改善が日常業務の中に自然に根付いていきました。
村田製作所:現場提案を制度として回す仕組み
同社は提案制度の設計にも工夫を凝らしています。
単に提案を募るだけでなく、提案が承認されるまでのスピードと成果の共有の仕組みを重視しました。
提案は数日以内に担当部署が検討し、可否や改善内容をフィードバック。
承認された提案はすぐに小規模で実験的に導入し、効果が出れば全社へ展開されます。この「短いサイクル」が従業員の納得感を生み、提案が「無駄にならない」という信頼感につながっています。
また、成果はイントラネットや掲示板を通じて全員に共有されるため、「誰かの改善が全員に役立つ」という感覚が組織に広がり、改善が個人の行為ではなく“会社全体の仕組み”として定着しているのです。
枚岡合金工具:5S徹底による工具探しのムダ削減
枚岡合金工具は、従業員30〜40名規模の中小企業ですが、大企業に負けない改善文化を築いた事例として有名です。
同社の5S活動は単なる整理整頓にとどまらず、「使う人の心理に寄り添った仕組み化」に特徴があります。
たとえば、工具を誰が戻しても必ず同じ位置に置けるように“型板管理”を徹底。さらに、探す時間をゼロにするため、「工具がどこにあるか一目で分かる」視覚的管理を徹底しました。
この工夫により、現場の従業員が即座に成果を体感でき、改善が「自分の仕事を楽にするもの」として浸透していきました。
改善は強制されたものではなく、「便利だから続けたい」という現場の実感によって支えられています。
これこそが、改善文化を定着させる最大の力となったのです。
枚岡合金工具:不良率30%低減と改善文化の定着
5S活動を基盤に、従業員が「もっと良くしたい」という声を出し合う雰囲気が社内に広がったことで、同社は不良率を30%低減しました。
注目すべきは、この成果が一部のリーダーの頑張りによるものではなく、現場全員が当事者意識を持ち、制度として改善に関与していた点です。
同社では改善提案を「評価のため」ではなく「全員が仕事をしやすくするため」に行うという文化を醸成しました。
改善が業務の一部として自然に繰り返され、やがて「やる気に頼らずとも動く仕組み」へと昇華していったのです。
成功企業に共通する要素と“始めやすい制度アイデア”

村田製作所や枚岡合金工具の事例から見えてくるのは、改善活動を持続させる企業にはいくつかの共通する要素があるということです。
本章では、それらを整理し、中小企業でも導入しやすい制度アイデアとして提示します。
目的共有:全員が理解できる改善目標の設定
成功している企業は、改善の目的を「コスト削減」や「件数達成」といった抽象的な目標に置くのではなく、従業員が腹落ちできる具体的なものに設定しています。
たとえば「工具を探す時間を半減させる」「不良率を3割減らす」といった目標は、現場の従業員が自分の業務と直結して理解でき、かつ改善達成後のメリットをイメージしやすいものです。
目標が具体的で共有されていれば、改善はノルマではなく「自分たちの仕事を良くするための活動」として浸透します。
活動の見える化:進捗と成果を共有する仕組み
改善が根付いている企業は、活動の進捗や成果を“見える化”して従業員に伝えています。
数字やグラフだけでなく、写真や動画、ビフォー・アフターの比較など、誰が見ても一目で分かる形で共有するのが特徴です。
改善の成果が実感を伴って共有されることで、従業員は「自分の取り組みが役立っている」という納得感を持てます。これは新たな改善の原動力となり、活動が継続するサイクルを生み出します。
小さな仕掛けの制度化:継続しやすい仕組みづくり
改善活動を制度として定着させるには、負担の少ない小さな仕掛けを積み重ねることが効果的です。
大がかりな制度設計を一度に導入すると、現場に負担が集中して挫折するリスクが高まります。
たとえば、週1回の短時間ミーティングで改善を話し合う、改善提案をホワイトボードに書き出してその場で共有する、といった仕組みでも十分に効果があります。
重要なのは、活動を日常業務に組み込み、「無理に続けること」ではなく「自然に続く仕組み」にすることです。
明日から始められる改善の第一歩

改善活動を仕組みとして定着させることが理想ですが、いきなり大きな制度を導入するのは現実的ではありません。まずは、どの職場でもすぐに始められる小さな一歩を踏み出すことが重要です。ここでは、明日から取り入れられる実践的な工夫を紹介します。
ホワイトボードで意見を集める
皆さんも経験があるかもしれませんが、意見を「会議で発表してください」と言われると、なかなか声が出ないものです。
得てして、会議で発言をする人というのは一部の人間に限られ、これが属人化の小さな種に繋がり得ます。
しかし、ホワイトボードに書き出す形式などにすると、不思議と意見が出やすくなります。
普段は黙っている人でも「気になること」「ちょっとした工夫」を気軽に書き残せるのです。
また、ホワイトボードに形として残ることで、他の人が残した意見を参考に、関連・発展させたような意見が出てくることも期待されます。
例えば「資材置き場が少し遠い」と書かれた意見を見て、「じゃあ台車の位置を変えてみたらどうか」と新たなアイデアが出る。こうした相乗効果が、1人の声では生まれなかった改善を引き出します。
週に1度、チームメンバーでホワイトボードを確認し、改善対象を決定する習慣をつければ、自然と小さな意見交換が生まれます。
「見える化」された意見は議題に上げやすく、改善の芽を拾い上げやすくなります。
提案をすぐに試す
改善の取り組みが続かない理由のひとつに、「せっかく出た意見が形にならない」という経験があります。
アイデアを出しても会議で終わってしまい、実行に移されないままでは、やがて誰も意見を出さなくなってしまいます。
そこで大切なのは、提案をできるだけ早く試してみることです。
大きな投資や根本的な変更は不要です。
まずは「仮にやってみる」くらいの感覚で構いません。
例えば「工具の置き場所を変えてみたらどうか」という提案なら、まずは一週間だけ配置を変えてみる。
その結果、作業時間が短縮できたのか、それともかえって混乱を生んだのかを確かめればいいのです。
このように小さく試す仕組みがあれば、提案が現場に反映されるスピードが上がります。
すると「出せばやってもらえる」という実感が芽生え、次の意見も自然と出やすくなります。
改善を「会議で終わる言葉」から「実際に回る仕組み」へと変えていくためには、スピード感のある試行が欠かせません。
記録に残す
改善活動は、その場で成果が出たかどうかだけを見て終わってしまうと、次に活かせません。
せっかくの工夫や学びが、個人の記憶の中に埋もれてしまうことを防ぐために欠かせないのが「記録に残す」ことです。
といっても難しい仕組みは必要ありません。
せっかくホワイトボードに提案内容を書いているのですから、そこに「試したこと」「結果」を書き足すだけでも十分です。
例えば「工具を右側に置いたら作業時間が短縮できた」と記録しておけば、同じ悩みを持つ別の部署にも展開できます。
逆に「うまくいかなかった」という結果も、次に同じ失敗を繰り返さないための財産になります。
記録が蓄積されると、改善は個人の経験から組織の知恵へと変わります。
さらに、自分の工夫が記録として残り、他のメンバーの役に立つことで「次も提案してみよう」という前向きな気持ちが生まれます。
自分たちの改善の結果が積み上がり、Before/Afterを比較することで、常に自分たちの成果を確認することができますよね。
記録は情報の保存であると同時に、改善を継続させるモチベーションにもなるのです。
おわりに
改善活動は一部の部署だけで取り組んでも長続きしません。組織として成果を出し続けるためには、会社全体で「改善が当たり前」という文化を育てていくことが不可欠です。
そのためには、経営層が目的を明確に示し、各部門での取り組みをつなげて全社的に共有する仕組みが求められます。小さな工夫を記録に残し、横展開することで、個々の知恵は組織の資産へと変わります。
改善を「担当者任せの活動」から「会社全体の成長戦略」へと位置付けることで、持続的な競争力を備えた企業文化が形成されていくのです。