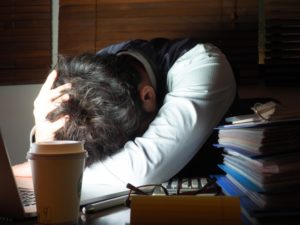整理・整頓・清掃を継続するために
3s活動、5s活動を続けるために
とても重要なポイントに
標準化と管理の定着が挙げられます
そんな標準化と管理の定着とは何か?
どうしてそんなに重要なのか?
標準化と管理の定着の進め方とは?
そんな標準化と管理の定着について
詳しく解説をしていくことで
あなたの職場づくりに活かして
いただければと思います
標準化と管理の定着とは?
まずはこの『標準化と管理の定着』
実はQC活動などで扱われている
QCストーリーのステップの1つで
問題解決の最終プロセスです
そのQCストーリーには以下のように
5ステップ存在しています
| 【QCストーリーの5つのステップ】 STEP1:テーマの選定 STEP2:現状の把握と目標の設定 STEP3:要因の解析 STEP4:対策の検討と実施 STEP5:標準化と管理の定着 |
4ステップで問題解決をして
この標準化と管理の定着でもって
◯元に戻らないようにすること
◯さらに効果の拡大を図ること、の
2つを狙いとしています
もう少し理解を深めていただくため
『標準化』と『管理の定着』に分けて
詳しく説明していきましょう
標準化とは?
標準化とは何でしょう?
まずは辞書を調べてみましょう
【標準化】ひょうじゅん‐か
1 標準に合わせること。また、標準に近づくこと。
2 何もしなければ多様化・複雑化し、無秩序になってしまう事柄について、秩序が保たれる状態を実現するために、誰もが共通して使用できる一定の基準を定めること。製品やサービスの品質・性能・安全性・互換性の確保、利便性の向上、試験・評価方法の統一などを目的として、統一された規格をつくる過程をいう。引用元: デジタル大辞泉by小学館
2つの意味が記載されてますが
この場合は2が近いです
ま、表現は少しむずかしいですが
要するに一定の基準を定めることです
例えば、あなたが自動車を運転して
時速65Km/hのスピードを
出していたとします
この状態は速いですか?遅いですか?
ま、確かに一般道では速いかもですが
高速道路では遅いかもしれません
もうおわかりでしょうか?
これを判断するには
つまり制限速度という標準が
必要になってくるわけです
制限速度が50Km/hの一般道路なら
15Km/hもオーバーしています
一方で同80Km/hの高速道路なら
15Km/hも不足していて
周囲の方々に迷惑をかけているかも
しれないということがわかります
つまり本来はどんな状態が適切か?
ちゃんと定めておこうというのが
標準化です
管理の定着とは?
管理の定着とは
文字通り管理を定着させることです
例えば整理・整頓・清掃を進めます
整理で必要なモノだけの職場にして
整頓でモノの置き方を標準化し
清掃でピカピカな状態にします
でもこの状態を維持していくためには
きっちりと手順を標準化したうえで
しっかりとそれを守る必要があります
ちゃんと標準どおりやれたかどうか?
どの程度やれているかどうか?
それをさらに進化させているか?
その状態をモニタリングする体制を
整備していくことを『管理』と呼び
それを定着させることが
『管理の定着』です
ではそれら標準化と管理の定着が
なぜ重要なのでしょうか?
なぜそんなに標準化と管理の定着が重要なのか?
職場では多くの改善を進めていきます
職場に存在する問題を見つけ出して
それを改善していきますよね
整理:不要なモノを捨てる
整頓:効率的な置き方を考えて標準化
清掃:ハキハキフキフキで磨き上げる
これを繰り返していきますと
1段階上の問題に気がついてきます
整理:なぜ不要なモノが発生するのか
整頓:なぜ決めても乱れてしまうのか
清掃:どこから汚れが生まれるのか
その根源をある日、見つけます
そうすると
不要なモノが発生しない方法
どうやっても乱れない方法
そもそも汚れが生まれない方法 を
考えつくようになります
でもこれは考えついただけだと
行動に移すのは自分だけです
多くの作業者は気が付かなくて
効果は限定的となりますよね
文字通り、そのヒトは気がついて
成長はしたかもしれないけれど
組織として成長できていません
これを組織ぐるみの成長へつなげる
そのためには改善して終わり!でなく
『標準化』で適切なやり方を決めて
それを管理して定着化させることで
限定的な効果を全体的な効果へと
拡大させることが重要になるわけです
ではそんな標準化と管理の定着は
どのように進めればいいでしょうか?
正しい標準化と管理の定着の進め方
標準化と管理の定着を進めるにも
正しい進め方があります
『標準化』と『管理の定着』にわけて
その進め方についてお話していきます
正しい標準化の進め方について
標準化とは適切なやり方を定めること
それを実現するために
『作業手順書』を作成します
作業標準書や作業マニュアルとも
呼ばれますが違いはありません
作業手順書の作り方は以下の
5つの手順でオススメします
| 【作業手順書の作り方】 手順1:作業手順書の内容を決める 手順2:目次や構成を考える 手順3:時系列順に手順を整理する 手順4:作業手順書を仮運用してみる 手順5:仮運用の結果で見直しする |
この5つの手順について
もう少しだけ詳しくお話しましょう
手順1:作業手順書の内容を決める
作業手順書をつくりはじめる時には
まず書く内容、つまり企画の内訳を
最初に決めておくことが重要です
なぜなら作成途中で目的を見失い
誰のための何のための手順書なのか
わかりにくい成果物になり勝ちに
なるからです
そのため5W1Hでまとめてください
い つ:When
どこで:Where
だれが:Who
なにを:What
な ぜ:Why
どのように:How
5W1Hは考えている内容を
具体的にするためのフレームです
そうやって内容を決めることが
1つ目手順です
手順2:目次や構成を考える
内容が決まったら次は
目次など構成を考えます
構成とは簡単に表現すると
作業手順書の大まかな枠組みです
絵画をデッサンするのにもかならず
全体の構図、骨組みを考えますよね
それと同じで作業手順書をつくるのに
しっかりと構成を組み上げてから
本格的に作成プロセスを進めて下さい
ただし、ここでは完璧を目指さずに
大まかであることが重要です
手順3:時系列順に手順を整理する
まずは作業手順をリストアップします
これを整理するには付箋が便利です
対象作業を実施している熟練作業者に
集まっていただいて作業手順を
教えてもらないながら付箋に記入し
それを模造紙に貼り付けていきます
不思議なことにこのプロセスだけで
意外と作業者によってバラツキがある
ことが明らかなって効果が出ます
それぞれの作業者が良かれと
各々工夫をしているためです
喜ばしいことですよね
でもそれぞれの考える最適な方法を
見つける過程であることを事前に
説明しておく必要があります
なぜなら今まで良かれと思って
工夫していることを否定されたと
誤解を受けかねないからです
そうなるとせっかく標準化しても
徹底しにく環境を作ってしまいます
ここは前向きなスタイルに対しては
歓迎ムードをつくれるよう
工夫して進めてください
そうやって手順を整理して
関係者で最適案をつくれたならば
それを文章化して次の手順へ
手順4:作業手順書を仮運用してみる
作成した作業手順書を配布して
まずは行って期間、仮運用してみます
そのことで
実際にそのとおり作業できるか?
期待どおりの効果がでるのか?
本当にその手順が最適なのか?
仮説を検証することができます
そしてその仮運用を進めてから
最後の手順に進めます
手順5:仮運用の結果で見直しする
仮運用で明らかになった問題点を元に
改善を折り込みながら見直します
そうやってより良い作業手順を
関係者全員でつくりあげていきます
このことによって熟練作業者が
気にしていることや考え方など
関わったヒトの理解が深まります
そういったものづくりに関する
スキルやノウハウも伝承できます
正しい管理の定着の進め方について
標準化がまとまったら次は
管理の定着を進めていきましょう
| 【管理の定着の進め方】 手順1:管理体制を検討する 手順2:検討した管理体制の仮運用 手順3:見直しと標準化 |
この3つの手順についても
簡単に説明していきましょう
手順1:管理体制を検討する
まずは関係者全員に集まってもらって
標準化した内容を全員で確認して
どんな管理体制が必要か考えます
作業品質を確認するチェックリスト
品質変動要因の数値グラフ(管理図)
不良項目別発生頻度のヒストグラム
など必要に応じてなにがベターか
そのことによって維持できるか
考えながら管理体制を検討します
これには答えというものがありません
さまざまな管理体制を検討して
最適なしくみを生み出して下さい
そして決めた管理体制も
一度文章化しておきます
手順2:検討した管理体制の仮運用
標準化と同じですが検討した体制を
一定期間仮運用して問題点を確認
明らかになった問題点を
忘れないようリストアップしておき
その対処法を考えておきます
手順3:見直しと標準化
そんな対処方を織り込んで
その管理体制を見直していきます
さらにそれそのものも
作業手順書として標準化しておきます
このことで担当が変わっても
やり方は分かりますし
新人教育にも活用することが可能です
標準化と管理の定着の進め方~5s活動の継続のために~まとめ
いかがだったでしょうか?
標準化と管理の定着の重要性と進め方
ご理解いただけたかと思います
ただし文章化とは表現しましたが
必ずしも書面化が適切とは思いません
最近ではスマートフォンの普及が進み
誰でも簡単にビデオが撮れて
ファイルの管理も簡単です
またパワーポイントで図式化しながら
音声を録音できて、これも動画化が
簡単にできるようにもなっています
こういったテクノロジーを活用すると
思っている以上に簡単に標準化と
管理の定着を進めることが可能なので
ぜひご検討ください
それでは今日はここまでです
今後とも宜しくお付き合いください☆
長文・乱文を最後まで読んでくださり
いつもありがとうございます♪
すべては企業発展のために
すべてはみんなの笑顔と元気のために