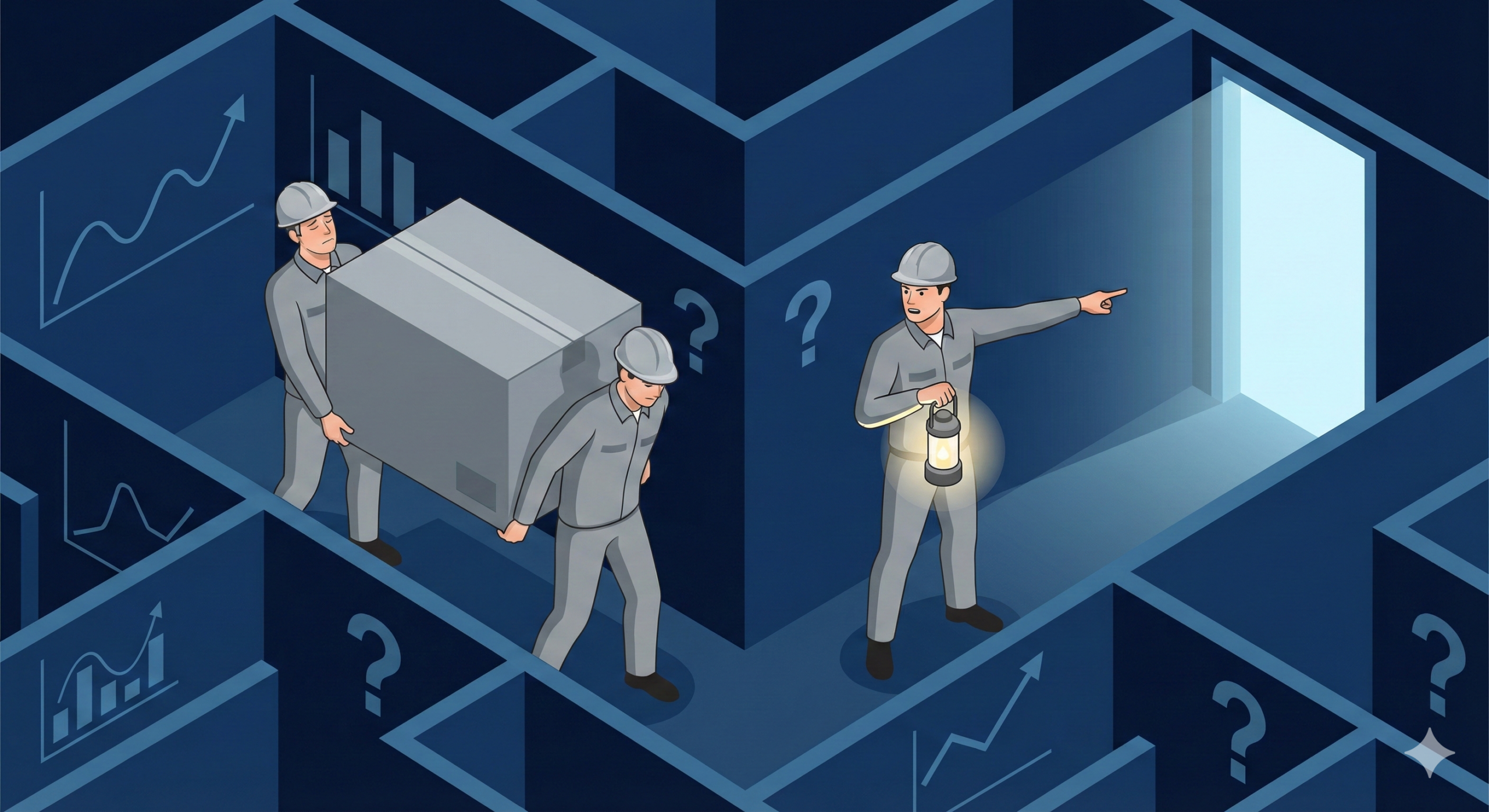こんにちは、中小企業診断士の吉岡です。
連載第2回では、QC活動を「現場を楽にするための実験」と再定義し、
パレート図などの道具をどう戦略的に使うかについてお伝えしました。
道具を絞り、6割の確信で動く。この「進め方」の型が見えてきたところで、
次に立ちはだかるのが「判断」の壁です。
「手順通りにやっているはずなのに、なぜかメンバーがついてこない」
「一生懸命旗を振っているのに、一向に成果に繋がらない」
こうした停滞を感じているなら、それは手法の問題ではなく、リーダーの無意識の判断ミスが原因かもしれません。
良かれと思って選んだテーマ、良かれと思って出した指示。
その一つひとつが、実は現場のやる気を削ぎ、活動を形骸化させる「罠」になっていることがあります。
第3回となる今回は、活動が止まってしまう現場の典型的な失敗パターンを解剖します。
何が活動のブレーキとなっているのか。
そして、止まりかけた活動をどうやって軌道修正させるのか。
リーダーが陥りやすい「判断の落とし穴」を回避し、停滞した空気を再び動かすための策を提示します。
QC活動が形骸化する現場の典型パターン
形骸化した現場を観察すると、そこには驚くほど共通した「負のパターン」が存在します。
これらは個人の能力の問題ではなく、活動の設計段階で形骸化することが半ば約束されているケースすら、見受けられます。
ここでは、それらを紐解いていきます。
テーマが現場の困りごとになっていない
最も多い失敗が、上層部が勝手に決める、テーマの押し付けです。
「会社の方針だから」「他部署がやっているから」という理由で、
現場の実感と乖離したテーマを設定すると、メンバーは一気に自分事として捉えなくなります。
たとえば、ある製造現場では「治具の建付けが悪く、加工のたびに微調整が必要で時間がかかる」ことに、
作業者全員が日々イライラを募らせていました。
彼らにとっての最優先事項は、この「一発で決まらないストレス」を解消し、少しでも早く仕事を終えることです。
しかし、リーダーは上層部から降りてきた「事務作業のペーパーレス化」を掲げてしまいました。
現場からすれば、「自分たちが今すぐ楽になりたい悩み」が置き去りにされた活動は、
単なる付け足しの業務でしかありません。
会社の体裁のためにやらなければいけない義務だ、と現場が認識をしてしまうと、
QC活動が活性化することは難しいでしょう。
また、そのような状況下で、リーダーが孤軍奮闘することも酷な話です。
そして、リーダー自身のモチベーションも削がれていってしまい、QC活動が形骸化してしまうのです。
成果が見えない活動
せっかく活動を始めても、いつまでも「現場が変わった実感」が得られないパターンも危険です。
完璧な分析や美しい報告書を目指すあまり、会議室での議論とデータ収集だけで
数ヶ月が過ぎていくケースは珍しくありません。
現場のメンバーが求めているのは、統計的な正しさよりも「今日から作業が少し楽になった」という手応えです。
分析ばかりが先行し、いつまでも具体的な対策(アクション)に移らないリーダーの下では、
メンバーは次第に「この時間は何のためにあるのか」と虚しさを感じ始めます。
報告書という「紙の上」での進捗ではなく、現場の風景が少しずつ変わっていく
「動的な進捗」を作れないリーダーは、活動のエネルギーを自ら奪ってしまっているのです。
前回の記事でも触れましたが、まずは分析は6割程度で構いません。
机上のデータと、現場の実感が合わさって初めて、効果的な改善策が生まれます。
まずは、データと現場を往復し、とにかく検証の数を増やすことを意識しましょう。
改善が評価に結びつかない
もう一つ忘れてはならないのが、活動の結果に対するリーダーのリアクションです。
ここで言う「評価」とは、人事考課ももちろん含みますが、それよりも日常のフィードバックを指します。
苦労して改善案を形にし、実際に効果が出たとしても、リーダーが
「指示のあったQC活動を行うのは当たり前」という態度で流してしまえば、メンバーのやる気は一瞬で霧散します。
あるいは、現場の知恵を「正規の手順ではない」と他部署から批判された際、
リーダーが守ってくれないという経験も、活動を形骸化させる強力な引き金になります。
話を俯瞰すると、日常業務のモチベーションや、会社への帰属意識にまで影響する大きな話です。
「頑張っても報われない、むしろ面倒が増えるだけだ」という学習性無力感が現場を覆ったとき、
QC活動は魂を失い、単なる作業へと変わってしまいます。
テーマ設定を誤ったときに起きること
QC活動が「苦行」に変わる最大の原因は、走り出す前の準備段階、すなわちテーマ設定にあります。
現場のリーダーが、良かれと思って掲げた目標が、実はメンバーを思考停止に追い込んでいるケースは
少なくありません。
ここでは、失敗を招く3つの代表的なパターンを見ていきましょう。
抽象的すぎるテーマの落とし穴
「品質意識の向上」や「ミスの撲滅」といった抽象的なテーマは、一見すると正論ですが、
現場はそれではついてきません。
なぜなら、メンバーにとって「具体的に明日、何を変えればいいのか」が全く見えないからです。
スローガンのようなテーマを掲げると、活動の内容も「注意喚起の徹底」や
「ポスターの掲示」といった、形だけの抽象的な対策に終始しがちです。
出口の見えない議論を繰り返すうちに、現場には「また精神論か」という空気が流れてしまいます。
また、テーマが抽象的過ぎると、QC活動の結果が良くても悪くても、会社として得るものはありません。
仮に結果が良かった場合、なぜ今回は上手くいったのかが言語化できません。
つまり、PDCAを回すことができず、再現性に乏しく次のQC活動に対する学びが得られないのです。
反対に結果が悪かった場合、「従業員の意識が足りない、徹底できていない」といった、
反省しかすることができず、これもまた従業員のやる気を削ぐ原因になります。
リーダーに求められるのは、耳障りの良い目標を設定することではなく、
問題を「誰が・どこで・何に困っているか」という手触りのある事実まで削り出すことです。
膨れ上がった「大きすぎるテーマ」
「工程全体のリードタイムを30%短縮する」といった壮大なテーマも、
現場を疲弊させる要因となります。
もちろん高い目標は大切ですが、日常業務を抱えながら取り組むQC活動において、
ゴールが遠すぎるとメンバーは途中で息切れしてしまいます。
一度に山を動かそうとすると、分析の範囲が広がりすぎて収拾がつかなくなり、
いつまでも「実行」に移ることができません。
その結果、数ヶ月経っても状況が変わらないことに焦りを感じ、
最後は報告書の帳尻を合わせるための「やっつけ仕事」に変わってしまいます。
特に本連載は、「これからQC活動を始めていく組織」を対象に執筆しています。
成功体験やノウハウがない中で、最初から壮大なテーマを掲げてしまうと、
なにからどのように着手すればいいかすらわからず、放置されてしまうというケースが多いです。
最終的に、QC活動を進めていく中で、取り組みたい対象として掲げておくことは否定しませんが、
従業員が育ち、QC活動が進んで現場の負担が減った将来に着手すべきです。
まずは小さな成功体験を積み重ねられるよう、テーマを適切なサイズに切り分ける
采配力がリーダーには不可欠です。
現場でコントロールできないテーマ
最もメンバーの無力感を誘うのが、自分たちの努力だけでは達成し得ないテーマを選んでしまうことです。
「原材料の品質を改善する」とか「設計図面の精度を上げる」といった、
他部署や仕入先が動かなければ解決しない課題を現場のテーマに据えてしまうパターンです。
どれだけ現場で知恵を絞っても、最後は「他部署の協力待ち」で活動が止まってしまう。
こうした状況が続くと、メンバーは「自分たちが頑張っても無駄だ」という不信感を抱くようになります。
自分たちがコントロールできる範囲をしっかり見極め、
そこを改善の対象に据えることが、チームの主体性を守るための大前提となります。
ただし、QC活動が文化として根付きつつある組織になった後には、この限りではありません。
QC活動を通じて、他部署との交流を行うこと自体は、組織活性化の面から悪いことではありません。
こちらも将来的な取り組み候補としては見据えつつ、「なぜ今ではないのか」を言語化しましょう。
そうすることで、現場から他部門にまたがる業務をQC活動の対象としたい、と要望があった時に、
モチベーションを削ぐことなく、「今ではない理由」を説明できます。
進め方を誤ったときに起きること
適切なテーマが決まり、いざ活動が走り出しても、そこには「進め方」という第二の壁が待っています。
リーダーが良かれと思って取った行動が、皮肉にもメンバーの主体性を奪い、
活動を収縮させてしまうことがあるのです。
現場の空気を停滞させる、リーダーの3つの振る舞いについて考えます。
リーダーが結論を先に出す「親切な支配」
経験豊富なリーダーほど、現場の問題を見た瞬間に「こうすれば解決する」という答えが見えてしまいます。
しかし、その答えを口にした瞬間に、QC活動は現場のものではなくなってしまいます。
リーダーが正解を提示してしまうと、メンバーにとっての活動は「自分たちで考える場」から
「リーダーの顔色を窺い指示をこなす場」に変わります。
あるいは、リーダーが考える正解以外を不正解として否定してしまうことも、
良く見られる支配的な形態の一つです。
たとえ遠回りに見えても、問いかけを通じてメンバー自身に気づきを促し、
彼らの口から解決策が出てくるのを待ってください。
そして、彼らの答えを許容してあげてください。
この「待ち、許容する度量」こそが、自走するチームを作るためのリーダーの器です。
そして、最終的にはリーダーであるあなたが関与することなく、QC活動や、その他の取組が回りだします。
最初はもどかしい思いをするとは思いますが、見守ることもまたリーダーの責務です。
「自由」という名の丸投げ
一方で、「自分たちで考えて自由にやっていいよ」と全てを現場に委ねてしまう放任も、
初期の組織では失敗の引き金になります。
特にノウハウが蓄積されていない段階において、具体的な指針のない丸投げは、
メンバーにとって「自由」ではなく「放置」と受け取られます。
日常業務に追われる中で、進め方の道筋も示されず、フォローアップもないままでは、
活動は優先順位の底に沈んでいくしかありません。
リーダーに必要なのは、放任でも強制でもなく、メンバーが迷ったときにいつでも立ち返り、
相談できる、適度な距離で伴走し続けるスタンスです。
現場の声を奪う「正論の壁」
会議の場で、一部の声の大きいメンバーだけが話し、
他のメンバーが沈黙を守っている状況は、形骸化の深刻なサインです。
特にリーダーが「データの根拠は?」「それは本当に効果があるのか?」と正論で詰めすぎてしまうと、
現場には「下手なことを言うと詰められる」という恐怖心が芽生えます。
心理的安全性が失われた場では、
メンバーは「黙っているのが一番安全だ」という処世術を身につけてしまいます。
現場の些細な違和感や「なんとなく怪しい」という感覚にこそ、真因を解く鍵が隠されています。
特に、QC活動を立ち上げてからすぐに、会議やミーティングの場で
積極的に発言ができる人材は限られています。
どうしても一人の意見に傾倒しがちになりますが、メンバー全員の意見を吸い上げるべく、
こまめなコミュニケーションを行うことを心掛けてください。
どんなに稚拙に見える意見でもまずは受け入れ、発言そのものを承認する。
その積み重ねが、形骸化の壁を突き破るボトムアップの活力を生むのです。
止まりかけたQC活動を立て直す視点
もし今、あなたのチームのQC活動が停滞し、メンバーの足が止まっていたとしても、悲観する必要はありません。
活動を「一度止める」ことや「やり直す」ことは、決して失敗ではないからです。
大切なのは、形骸化したままズルズルと続けるのではなく、
リーダーが勇気を持って「軌道修正」の旗を振ることです。
現場を味方につける「説明と説得」の技術
テーマを修正する際、最も重要なのがメンバーへの言葉の尽くし方です。
QC活動が上手くいかない原因として、推進側と現場の温度感の違いがあげられます。
QC活動は、達成さえされれば現場の負荷は減る/生産性が上がることは事実ですが、
過渡期においては現場の負荷が増すこともまた事実です。
ビジョンや将来像が提示できないまま、取組を推進したとしても、
現場は負荷が増えたようにしか感じません。
温度感に差があって取り組みが進んでいかない場合には、ビジョンを共有し、この取組が最終的には自分たちのためになるということを、現場に理解してもらうことから始めましょう。
当然ですが、QC活動の担い手は、最終的には現場です。
そして、皆様は現場のリーダーなので、比較的現場に近い位置に属しているはずです。
皆様にしかかけられない言葉や、伝えられないメッセージがきっと存在しています。
勇気を持って「テーマを見直す」
活動が止まる最大の理由は、これまで述べた通りテーマが身の丈に合っていないことにあります。
数ヶ月経っても一歩も進んでいないのであれば、
思い切ってテーマを「今の自分たちが確実に解決できるサイズ」まで小さく削ぎ落としてみてください。
「工程全体の改善」が重すぎるなら、「この棚の配置一つ」まで絞り込む。
全社目標が遠すぎるなら、自分たちが毎日イライラしている「あの治具」の話にすり替えても構いません。
リーダーが「まずはここだけを確実に楽にしよう」と目標を再定義することで、
現場の空気を変えることを試みてください。
「進め方」を修正し、メンバーの手に返す
もしリーダーが先走りすぎていたと感じるなら、一度立ち止まってメンバーにボールを渡しましょう。
これまでの結論を白紙に戻す必要はありませんが、
「実は私も少し焦っていた。もう一度、皆が本当に困っているところから教えてほしい」と素直に伝えることが、
現場の信頼を取り戻す第一歩になります。
リーダーが完璧な指揮官であることをやめ、現場の「困りごと」を拾い上げる伴走者に徹したとき、
メンバーの中に「自分たちの活動だ」という当事者意識が芽生え始めます。
進め方を修正することは、リーダーの敗北ではなく、チームを自走させるための高度な戦略的判断なのです。
途中修正を「失敗」にしないマインドセット
最も重要なのは、こうした軌道修正を「失敗」と捉えないことです。
第1回で述べた通り、QC活動の本質は「実験」です。
テーマが大きすぎて動けなかった、あるいはリーダーが口を出しすぎて空気が冷めた。
これらすべては「このやり方ではチームは動かない」という貴重なデータ(発見)に過ぎません。
「上手くいかなかったから、やり方を変えよう」と明るく宣言し、前向きに修正を繰り返す姿こそが、
第1回で掲げた「前進を評価するスタンス」の体現です。
リーダーが修正を恐れず、軽やかにハンドルを切る姿勢を見せることで、
現場には「失敗しても大丈夫だ」という安心感が生まれます。
そして、それが結果として持続可能な改善文化を育てていくことになります。
おわりに
連載第3回を通じ、QC活動が形骸化するメカニズムとその打破について考えてきました。
QC活動は、決してリーダーがメンバーを管理するための道具ではありません。
現場で汗をかく一人ひとりが、自分の仕事に誇りを持ち、自らの手で職場をより良くしていくための「武器」です。
その武器が錆びつき、重荷になっているのであれば、一度下ろして磨き直せばいいだけの話です。
QC活動が活きた活動になるか、停滞してしまうかはリーダーの采配が大きなカギを握ります。
是非、本記事の内容を参考に活きたQC活動を立ち上げて下さい。