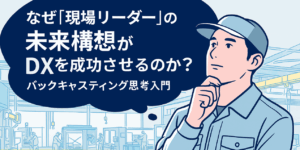皆さんは普段、設備の調子を見ながら、頭の中でパズルを解くように「今日はここを調整しておこう」「そろそろあそこが摩耗してきそうだな」と段取りを考えているはずです。その熟練の技、実はもっと楽に、チーム全体で共有できる「武器」に変えられることをご存じでしょうか。
「DXだ」「データ活用だ」と聞くと、なんだか仕事を監視されるようで身構えてしまうかもしれません。しかし、今回ご紹介するのは管理のためのツールではありません。私たちが現場で感じている「なんとなく変だ」という違和感を、既存の設備に新たな機能(SCADAやPLC)を使って見える化し、理不尽なドカ停や急な呼び出しをなくすための「現場主導の仕掛け作り」なんです。
なので高額なシステムや専門知識なんて必要ありません。今の環境のまま、生産性を上げ、かつ仕事をスマートに回すための「現場の知恵の活かし方」について、具体的な手順をお話しします。
ものづくりの現場では、私たち「ヒト」の判断力と、「設備」のパワーが組み合わさって初めて価値が生まれるもの。それを言わば職人でなくても、誰でも事前に予防的なアプローチを取る=予兆保全のための組織的なしくみをつくる。
今回はそんなアイデアのひとつとして知っていただきたいと思います。
今回も読み終えるまでのお時間、しばらくお付き合いくださいませ。
そもそも「予兆保全」と「SCADA」とは? 現場を楽にするための基礎知識
本題に入る前に、まずは今回のキーワードとなる「予兆保全」と「SCADA(スキャダ)」について、現場での使い勝手という視点から整理しておきましょう。
これらは単なる管理者向けの難しい用語ではありません。私たちの「目」や「耳」を拡張し、仕事をスムーズに進めるための便利な道具(拡張機能)なんです。
1. 予兆保全とは?
- それは何か?(定義):これまで一般的だった「壊れてから直す(事後保全)」や「期間を決めて部品を全交換する(予防保全)」とは違い、「設備が上げ始めた小さな悲鳴(不調のサイン)を察知して、壊れる直前にサッと手当てすること」を指します。人間で言えば、倒れてから入院するのではなく、少し熱っぽい段階で薬を飲んで治すイメージです。
- 現場でのメリット:最大のメリットは、「自分たちのペースで仕事ができる」点です。突発的な故障(ドカ停)による緊急対応や、部品待ちのアイドルタイムといった「理不尽な忙しさ」をなくし、計画通りにメンテナンスを行えるようになります。
- 具体的な使い方:「いつもよりモーター音が大きい」「シリンダーの動きがコンマ数秒遅い」といった違和感をキャッチし、完全に止まる前に部品交換や調整を行います。
2. SCADA(スキャダ)とは?
- SCADA(スキャダ)とは何か?(定義):現場にあるたくさんの設備やセンサーの情報を、パソコンやタブレットの画面に集約して「リアルタイムで見える化する監視システム」のことです。PLC(制御装置=製造設備用のPCの役割)が設備の「脳みそ」だとしたら、SCADAはそれを人間に分かりやすく表示してくれる「コックピットのモニター」のようなものだと考えてください。
- 現場でのメリット:設備の中で起きている「見えない変化(電流値の揺らぎや圧力の低下など)」が、グラフや数値としてひと目で分かるようになります。これにより、ベテランさんが肌感覚で持っている「そろそろヤバいかも」という予感を、客観的な事実としてチーム全員で共有できるようになります。
- 具体的な使い方:新しい難しい機械を覚える必要はありません。今あるPLCのデータをSCADA画面に表示させ、「この数値がここまできたら注意」といったルールを設定して使います。いわば、設備の健康診断書を常に見られる状態にするツールです。
なぜ「データの蓄積」だけでは設備管理DXは失敗するのか
「とりあえずセンサーをつけて、データをクラウドに上げておこう」
DXという言葉が流行ってから、こんな号令で現場が振り回される失敗例をよく耳にします。
実は、どれだけ高性能なサーバーにテラバイト級のデータを溜め込んでも、それだけでは現場は1ミリも良くなりません。ここでは、よくある「データ収集の罠」と、本来私たちが目指すべき「活きた仕組み」について考えてみましょう。
データは「意味」とセットでないとゴミになる
まず押さえておきたいのは、「判断基準のないデータは、ただのノイズ(ゴミ)である」という厳しい現実です。
- ただのデータ: 「10時のモーター温度は65℃でした」「振動値が0.5mm/sでした」
- 現場に必要な知恵: 「いつもより温度上昇が5分早い。これはグリス切れの予兆だから、昼休憩に給脂しよう」
現場の私たちが欲しいのは、単なる数字の記録ではありません。「で、どうすればいいの?」というアクションに直結する「判断のための知恵」ですよね。この「意味付け」を行わずにデータだけを集めても、誰も見ないグラフが増えるだけで終わってしまいます。
現場の中心人物が担う本当の役割
では、現場を回す中心的な立場にある私たち(リーダー格やベテラン)は、何をすればいいのでしょうか。それは決して、高価な分析ツールを選定してくることではありません。
一番大切な仕事は、作業中にベテランの仲間が漏らす「なんか今日、音が変だな」「ちょっと振動がピリつく気がする」という違和感をスルーせず、掘り下げて言語化することです。
- 「どのタイミングで変だと感じたのか?」
- 「その時、どこを触って熱を確認していたのか?」
この「現場の感性(気づき)」と「データ(事実)」の会話を成立させること。つまり、「あの時の違和感は、データで見るとこの波形の乱れだったんだな」と答え合わせができる環境を作ることこそが、本当に役立つ設備管理の第一歩になります。
ステップ1:守るべき設備の特定と「劣化メカニズム」の整理
新しい取り組みを始めるとき、一番やってはいけないのが「あれもこれも全部監視しよう」と欲張ることです。いきなり全ての設備にセンサーをつけようとすれば、設置の手間だけで現場はパンクし、結局誰もデータを見なくなってしまいます。
まずはリソース(手間と予算)を一点集中させ、確実に成果が出る場所から攻めるのが鉄則です。
優先順位の決定(重要度×リスク)
最初にやるべきは、私たちの工場にとっての「急所」を見極めることです。以下の2つの視点で、対象設備を1〜2台まで絞り込んでみてください。
生産影響度と故障リスクのマトリクス
頭の中にある「止まると怖い設備」を、少し具体的に評価してみましょう。
- ライン全体への影響: 「これが止まると、後工程も含めて全員の手が止まってしまう」というボトルネック設備はどれでしょうか?
- 復旧の難易度: 「替えの部品が海外製で、納期が3ヶ月かかる」「修理できるメーカーの技術者がなかなかつかまらない」といった設備はありませんか?
【アクション】
この2つの要素を掛け合わせ、「一番止まってほしくない設備」をターゲットに決めます。まずはその1台だけでOKです。成功事例ができてから横展開すればいいのですから。
熟練工へのヒアリング(仮説の立案)
監視対象が決まったら、次は「何を監視するか」を決めます。ここで頼りになるのが、その設備を一番よく知っているベテランさんの経験則です。
「異常の前」に何が起きているか?
ここで重要なのは、質問の仕方です。ベテランさんに「この機械、次はいつ壊れますか?」と聞いても、「予言者じゃないんだから分かるか!」と怒られてしまいますよね。聞くべきなのは「時期」ではなく「予兆」です。
【現場で聞くべき質問】
- 「壊れる前って、どんな音がし始めますか?」
- 「調子が悪くなるとき、いつもどこを触って熱を確認していますか?」
- 「製品のバリが増えるとか、削りカスが変わるとか、前触れはありますか?」
こうして聞き出した「音」「熱」「振動」「動作の遅れ」などの情報こそが、これから私たちがデータで捕まえるべき「正解データ(仮説)」になります。AIに頼らなくても、現場にはすでに答えを知っている人がいるのです。
ステップ2:感覚の「翻訳」とデータの可視化
ステップ1で集めた「ベテランの五感(アナログ情報)」を、今度は機械が理解できる「デジタル値」に置き換えていく作業です。いわば、職人のカンを数値という共通言語に「翻訳」するプロセスです。
「使えるデータ・足りないデータ」の棚卸し
「予兆保全=新しいセンサーを買うこと」だと思い込んでいませんか? 実は、それは少し違います。
既存タグ(PLCデータ)の確認
私たちの現場にある設備の制御盤(PLC)の中には、すでに膨大なデータが流れています。まずは手持ちのカードを確認しましょう。
- 電流値・電力値: 負荷のかかり具合を表す基本データ。
- サイクルタイム: 1工程にかかる正確な秒数。
- サーボ負荷率・トルク値: ロボットや駆動系の疲れ具合。
【重要】
多くの現場では、追加投資をしなくても、すでにPLCの中に「お宝データ」が眠っています。「センサーを買う前に、ラダープログラムの中にある数値をSCADAで拾えないか?」を電気担当や保全担当と相談してみてください。意外と多くのヒントが既にそこにあります。
感覚とデータの対応表(翻訳マップ)の作成
次に、ステップ1で聞いた「異常の前触れ」を、具体的なデータ項目と紐付けていきます。これを私たちは「翻訳マップ」と呼んでいます。
「熱っぽい」→「温度データ」への変換
熟練工の感覚を、物理的なパラメータに変換してみましょう。
- 「モーターが唸っている気がする」
- 翻訳案A: 電流値の波形が乱れていないか?(PLCデータで対応可能かも)
- 翻訳案B: それとも振動が出ているのか?(ここで初めて振動センサーを検討)
- 「シリンダーの動きがなんか渋い、遅い」
- 翻訳案: 指令を出してからオートスイッチが入るまでの「到達時間」が、通常より0.1秒伸びていないか?(PLCのタイマー監視で対応可能)
【アクション】
このように整理すると、「PLCの中にあるデータで分かること」と「新しくセンサーを付けないと分からないこと」が明確になります。やみくもに高価なセンサーを付けまくるのではなく、この翻訳作業を通じて「本当に必要な足りないデータ」だけを特定して投資するのが、賢い現場のやり方です。
ステップ3:AI不要!「ルールベース」での予兆検知モデル作成
「予兆検知」と聞くと、すぐにAI(人工知能)やディープラーニングといった難しい言葉が飛び交いますが、現場の感覚からすると、中身の分からない「ブラックボックス」に判断を任せるのは怖いですよね。
「なぜアラートが出たのか?」が説明できないシステムは、現場では定着しません。まずは私たち人間が納得できる「明確なルール」を作ることから始めましょう。実はAIを使わなくても、SCADAの計算機能だけで十分な成果が出せるんです。
データ×現場知のハイブリッド分析
まずは、ステップ2で集めたデータが本当に使えるか、過去の実績を使って検証します。
過去トラブルの時系列データ検証
保全記録をひっくり返して、過去に故障した日時を特定してください。そして、そのタイミングのデータをグラフにして、ベテランさんと一緒に眺めてみます。
- 「ほら、故障する2日前のここ、電流値がたまに跳ね上がってるだろう?」
- 「あ、本当ですね。普段は平らなのに、ここだけギザギザしてます」
このように「ベテランの記憶」と「実際の波形」の答え合わせを行うことで、「どのデータが乱れたら危ないか」という確信(エビデンス)が得られます。
「兆し」の定義と閾値設定
次に、SCADAに設定するアラートの条件(閾値)を決めますが、ここにはコツがあります。単に「〇〇を超えたらアウト」という設定では、予兆検知にはなりません。
単純な閾値ではなく「変化」を捉える
故障の予兆は、絶対値ではなく「いつもと違う動き」に現れます。
- NG例(単純な閾値): 「温度が50℃を超えたらアラート」
- これでは「すでに壊れかけている」あるいは「夏場だから暑いだけ」という可能性があり、手遅れか誤検知のどちらかになりがちです。
- OK例(変化を捉えるルール):
- 継続時間の監視: 「通常より10%高い状態が、30分以上続いた」
- 立ち上がりの監視: 「朝一番の始動時間が、先月の平均より0.5秒遅い」
- バラつきの監視: 「電流値の揺らぎ幅(標準偏差)が、いつもより大きくなった」
こうしたロジックであれば、難しいAIプログラムを書かなくても、一般的なSCADAの設定だけで実装可能です。「閾値を超える前」の「変化」を捕まえることこそが、予兆保全の醍醐味です。
ステップ4:知恵を蓄積し続ける「循環サイクル」の構築
SCADAを導入し、ルールを設定したら「はい、完了」ではありません。そこはゴールではなく、ようやくスタートラインに立った状態です。
現場の道具と同じで、この予兆検知システムも「使い込んで、自分たちの手に馴染ませていく(育てていく)」必要があります。ここからの運用こそが、本当の意味での「強い現場作り」になります。
予兆検知後のフィードバックループ
最初に決めた閾値(ルール)が、最初から100点満点であることはまずありません。「アラートが鳴ったけど、何も起きていなかった(空振り)」ということも当然あります。重要なのは、それを失敗と捉えずに「調整のチャンス」と捉えることです。
「当たり・外れ」の記録
アラートが出た際、実際に現場へ行って点検した結果を必ず記録してください。
- 当たり: 「行ってみたら、本当にボルトが緩んでいた!」→ ルールは正解です。自信を持って運用しましょう。
- 外れ: 「点検したけど、異常はなかった」→ ルールが少し厳しすぎたかもしれません。
【今後の最初の一手】
外れだった場合は、「なぜ誤検知したのか?」を考え、閾値を少し緩めたり、監視する時間を延ばしたりして修正します。この「運用しながらルールを磨き上げる繰り返し」こそが、メーカー製のAIには真似できない、その現場独自の「生きた知恵」になっていきます。
感性を知恵に変える組織文化
この仕組みが動き出すと、現場での会話が変わってきます。
- 若手・新人: 「画面の数値が、規定のラインを超えそうです!」(データの報告)
- ベテラン: 「その波形なら、たぶん吸着パッドの汚れだ。フィルタを見てみろ」(経験からの判断)
これまでベテランの頭の中だけにあった経験則が、データを介することで若手にも共有されるようになります。そして、「どんなデータが出た時に、どう対処したか」という履歴を残すこと自体が、特定の個人に依存しない「最強の技術伝承(マニュアル)」になります。
「背中を見て覚えろ」ではなく、「データを見て、一緒に考える」。これこそが、現代の現場に求められている技術継承の新しいカタチではないでしょうか。
まとめ:熟練工の「違和感」をSCADAでデータ化する4つの手順
今回は、高価なAIシステムに頼らず、現場の「勘とコツ」をデジタル技術で武器に変える方法についてお話ししました。
改めてお伝えしたいのは、「DXの主役はあくまで現場の人間である」ということです。データは、私たちが楽をするための、そしてより良い仕事をするための「道具」に過ぎません。
最後に、今回ご紹介した4つのステップを振り返っておきましょう。
- 一点突破で始める:いきなり全設備を監視せず、止まると一番痛い「重要設備」に絞る。
- 五感を翻訳する:熟練工の「音」「熱」「振動」といった違和感を、対応するデータ(タグ)に紐付ける。
- ルールを作る:ブラックボックスなAIを使わず、過去データと照らし合わせて「人間が納得できる閾値(ルール)」を作る。
- 育てていく:運用しながらルールの当たり外れを検証し、組織全体の「知恵」として蓄積する。
この手順を踏めば、特定のベテランさんしか分からなかった「設備の機嫌」が、チーム全員の手でコントロールできるようになります。それは結果として、休日出勤や深夜の呼び出しといった「理不尽」から、私たち自身を守ることにも繋がるのです。
今日からできる最初の一歩
まずは明日、現場に行った際に、自社の最重要設備についてベテランの保全員の方と「過去の故障前に、どんな予兆(音や動きの変化)があったか」を雑談レベルで話すことから始めてみてください。
「あの時は、なんかモーターが唸ってたんだよな」「動きが少しカクついてたんだよ」
そんな会話の中に出てきたキーワードこそが、あなたが最初にモニタリングすべき「データ項目」の正解です。
ぜひ、あなたの現場にある「埋もれたお宝データ」を掘り起こして、よりスマートでかっこいい現場を作っていってください。応援しています。